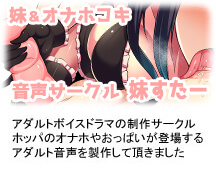オナホ文学とは

「オナホ文学」とはオナホールに込められた世界観をより楽しむために製作された大人の文学です。
小説?ラノベ?芸術?
いえ、オナホです。
熱可塑性エラストマーです。
大人が作りたがる定義なんて原材料と一緒に加熱してしまいましょう。
 |
【今回の対象品】 くノ一淫法 触手裏剣 番外編~椿の憂鬱~ 触手裏剣 すじズリ |
一.椿
淫賀の里のくのいちの修行は過酷だ。
彼女たちはまず生まれた時に性器の検査を受ける。
その形状が男を悦ばせるのに不適であったり、色が男の劣情をそそるものでない場合、この時点で振り落とされ、人知れず始末されてしまうのだ。
言葉が話せるようになるまで成長すると、ありとあらゆる淫語を覚え込まされる。
これは将来その場の状況に合わせ男の感情を自在に操れるようにするためだ。
最初は意味も教えずただ繰り返させるだけだが、次第にその意味を教え、最も適切な状況で使う技も覚えさせていく。
もちろん、ここで「物覚えの悪い娘だ」と見做された場合も、人知れず始末されるのだ。
さらに長じて七歳になると、運命の日が訪れる。
彼女の前に、三宝に載せられた竹の筒が置かれる。
竹の筒の片側は丸く整形され、磨かれてすべらかになっている。
くのいち候補はそこで教師役のくのいちたちに服を脱がされ、手足を押さえつけられた上で竹筒を膣内に挿入されるのだ。
無論、この時に処女膜は破られる。
これを「竹初め」と言う。
竹初めの儀式が済むと、少女は己の膣内から取り出された竹筒を咥えるように命じられる。
口に含まれた竹筒の反対側に、穴が穿たれ紐が通される。
そして竹筒は口枷のように少女の頭部に固定されるのだ。
教師役のくのいちたちはこの時、少女に「口の中の竹筒を常に舌でねぶりつづけるように。寝ている時も例外ではない」と命じる。
これは誇張でもなんでもない。
それから毎夜、少女たちが口を動かさずに眠っていると、教師役のくのいちたちは容赦なしに竹鞭で少女の体を叩くのだ。
教師役たちは少女が憎いわけでも、嗜虐的な嗜好を持っているわけでもない。
くのいちである以上敵に捕らわれ、四肢を縛り付けられた上で拷問を受けることも十分あり得る。
蠱惑的な肢体を持っているが故に、犯されることもあるだろう。
だが意識を失っても舌が動いていれば、敵の精力を吸い付くして昏倒させ、逃げ延びる機会を得ることができるのだ。
口に竹筒を咥えさせられた少女の膣口には、別の竹筒があてがわれる。
片側が丸く整形され磨かれているという点は口の竹筒と同じだが、こちらは中に小さな鼠が餌とともに仕込まれている。
竹筒の中で鼠が餌を食えば、その時生じる微妙が振動が竹筒を通して膣に伝わる、という仕組みである。
これによりいかなる場合においても敵の精力を吸えるようにするとともに、自らを襲う快感を支配して、任務を遂行する精神力を養うのだ。
上下の竹筒は、日に数度外していいと言われる時がある。
それは教師役との「房中術」の修行の際である。
口の竹筒に関しては、食事と飲水の時も外すことが認められていた。
「房中術」はくのいちにとって最も重要な、床の中で敵を手玉に取るための秘術である。
この修業は大きく前期と後期に分けられる。
前期の修行は、主に教師役のくのいちとともに行う。
まだ成熟しきらない肉体を開発し、性技がいかに効果的に相手を支配できる技であるかを、自らの体を持って知るのである。
またこれは、将来女性を相手に任務を遂行する場合の訓練も兼ねている。
くのいちがその肉体で籠絡する相手は、男とは限らないのだ。
大名の正妻はほとんどが政略結婚により嫁いだものである。
このためほとんどの大名は自己の性欲を満たすために側室愛妾を持つ。
夫に相手にされず性的欲求を満たせなくなった正妻は、極めて「落としやすい」相手になるのだ。
また女同士である、ということで、警戒されずに接近することもできる。
全身の性感が十分に開発された、と教師役のくのいちが判断すると、相手は男の忍びに代わる。
ある意味これまでの修行はすべて前座で、ここからが真の修行と言えるだろう。
彼女たちはここで、いかに快感に流されずに相手の精力を枯渇させ、あるいは自らの肉体に溺れさせ思いのままに操れるようにするための技術を学ぶのだ。
実は彼女らが生まれて初めて男に触れるのは、この教師役交代の時なのだが、「処女」を失ったことに特別な感慨を持つくのいちはほぼいない。
彼女たちの秘部はこれまで数限りなく竹筒に貫かれているからだ。
もちろん、これは性に関することに対して驚いたり戸惑ったりすることなく、常に冷静に適切な行動を取ることができるようにと、淫賀の里ぐるみで築き上げてきた指導体制の成果である。
性の悦びを好ましいものと考えていなければ、相手を自分の肉体に溺れさせることはできない。
しかし、性のすべてを知り尽くし、うろたえることなく常に上位に立てなければ、相手の肉体の虜になってしまう。
里の教えはこの微妙な立ち位置を意識せずに保てるようにと、長い年月をかけて培われてきたものなのだ。
こうして彼女たちは十五の年まで修行を続ける。
無論脱落したものは人知れず始末される。
十五になり、一人前になったと認められた彼女たちは、くのいちとして全国に散らばり、その任務を遂行することになるのだ。
椿は淫賀の里の中でも傑出した存在だと認められたくのいちだ。
まずは出生の際、その性器の美しさに産婆が見惚れたという逸話を持つ。
淫語の覚えも他のくのいち候補よりも遥かに早く、六歳の頃には教師役すら知らない淫語を口にしていた。
教師役が不審に思って調べたら、里の牢内に囚われていた忍びから聞き出した他国の淫語であったという。
七つの時の竹初めの時には、挿入時の声のあまりの甘やかさに、竹筒が絶頂、射精したとも伝えられている。
その後の修行においても、我を忘れて椿の肉体に溺れてしまった教師役は数多くいた。
椿の最初の相手となった男忍びは、床において椿が恥じらいを見せ処女のごとく(男相手には確かに処女だが)身をくねらせたため己が任務を忘れ果て、五度もその膣内で射精してしまったという。
直後、この男忍びは房中術の教官としての任務を解かれ、戦忍びとして戦場に送られ、程なく戦死したという。
彼以外にも、椿の相手をしたことにより教官を罷免された忍びは、男女を問わず十人ほど出た。
淫賀の里の長老たちは苦り切った。
椿が類稀ない房中術の天才であることは間違いがない。
それは里として喜ばしい。
だが天才過ぎるがゆえに次々と教官役を壊してしまう。
このままでは他のくのいちの育成にも支障をきたしてしまうだろう。
長老たちは額を突き合わせていかにすべきか何日も話し合ったが、名案は出ない。
だが、ある時ふらりと合議の場に現れた「お館様」の一言であっさりと結論が出た。
「お館様」はこう言ったのだ。
「それほど優れたくのいちならば、何をためらうことがあろう。今すぐ修行は全部終わりということにして、現場に送ればよいのだ」
これは長老たちにとっては盲点であった。
彼らの頭の中には、「修行は十五まで」という掟がこびり付いていたのだ。
なぜなら、それは里が気の遠くなるような期間守り続けていたものだったから。
彼らは「掟を変える」という発想がなく、これまで「掟の中で椿の教育をどうするか」ということしか論じて来なかったからだ。
長老のひとりが恐る恐る、「十五まで育てるのが里の掟であります」とお館様に言上した。
だが「お館様」は静かに微笑みつつこう言った。
「里始まって以来の逸材なのであろう? ならばこれまでの里の掟で縛ることはできぬし、その必要もなかろう」
一同、これに服した。
老いてものの考えが固くなっていたとはいえそこは忍びである。
特殊なものを一般的な規範で縛ろうとすることに意味はない、特に忍びの場合そうした発想は死に直結する、ということを皆体験的に知っていた。
「お館様」は淫賀の里の忍びを代々束ねる腿痴家の当主である。
五年前に逸物が勃たなくなり自害した先代の後を継承した。まだ若い。
普段は着流しに羽織をひっかけ、長い髪を束ねもせずに背中に垂らした姿で里の中をゆったりと歩き回っている。
そして里のものの背後から体調はどうだとか悩みはないかとかのねぎらいの言葉をかけていた。
かように無害そのものといった日常を送っている「お館様」だが、里の忍びは手練になればなるほど彼を恐れていた。
「お館様」が背後から忍び寄った時の気配を感じることができないからである。
「お館様」が忍びの術を振るっている姿を誰も見たことはないが、彼らの想像をすら超える厳しい修行を経験していることに気づいた忍びは少なくなかった。
恐らくは先代が誰にも知られないような形で鍛え上げたのであろう。
また里のくのいちの多くは、「お館様」に声をかけられてその身が濡れてしまう、という体験を持っていた。
「お館様」に見られただけで体の芯が熱くなってしまい、そこらの家に飛び込んで激しく何度も自慰をしてしまったという手練のくのいちも多い。
こちらの方でもかなりの修行を積んでいると想像されるのだが、誰とどのような形で修練したのかはまったくわからなかった。
現在、「お館様」は妻を娶っておらず、里の娘、つまり若いくのいちを自分の館に引き込んだという話もない。
里のものは全員が穏やかで優しい言葉をかけてくれる「お館様」に親しみの情を持っていた。
だが同時に、その隠された能力の底知れなさに恐怖も感じていたのである。
「お館様」の提案がすぐさま長老全員から承認されたことの裏には、こうした事実があったのである。
かくして椿が呼び出され、「お館様」の御前へと出た。
椿、齢十三。
これが「お館様」への初お目見えである。
椿はこれまで、「お館様」から声をかけてもらったことがなかった。
恐らく里の中では唯一の存在だろう。
お忍びで里の中を歩き回っている「お館様」だが、下忍たちとの間には超えられない身分の差というものがある。
このため正式な「お目見え」の儀式においては、下忍であるくのいち・椿は庭の白砂の上に平伏し、庭に面した部屋の奥から「お館様」が声をかけるという形になった。
白砂の上に座った椿は、その時から不思議に体が熱くなるのを感じた。
まだ壇上の部屋に「お館様」はお出ましになっていない。
やがて遠くから、静かな足音が聞こえてきた。他の忍びにはまず気づかれることのない、気配を消した足さばきだったのだが、椿は全身で「お館様」の接近を感じ取ったのだ。
「お館様」の足音、いや気配は椿の体内で反射し、増幅されて陰核へと伝えられる。
「足音」が近づくごとに、椿は自分の陰核が「お館様」の足指でこねられているかのような感覚を覚えた。
最初は静かに遠慮気味に、だが次第にこねる速度が上がり、圧力も強くなる。
椿の身が濡れる。
喘ぎ声が漏れそうになる。
椿は必死で耐えた。
齢十三にしてすでに里に並ぶものはないほどの達人になった椿である。
どんな強い快感に襲われても、周囲の忍びに喘ぎ声を悟られるという失態は犯さない。
だが、椿はほんの少しでも声を漏らせばそれは「お館様」の知るところとなる、ということを理解していた。
階上の部屋の襖が開く。
春の風のようにふわりと、「お館様」が部屋に入り、奥に敷かれた畳の上に座った。
物音ひとつしなかったが、椿の体内にはこれまでよりも強い衝撃が伝わった。
衝撃はまたも椿の体内で増幅し、陰核へと至る。
椿は達した。
周囲の忍びは誰一人気づかなかったが、「お館様」には知られてしまったと、椿は思った。
「そんなにかしこまらなくてもいい。頭を上げなさい」
「お館様」は椿に声をかけた。
周囲の忍びは、くのいちも含めていつも通りの穏やかさをその声音に感じ取った。
しかし椿には、「お館様」の声は首筋から衣の前に滑り込み、椿のまだ小さな乳首をこねくり回し、成長の余地を残した乳房の根本を撫で、臍から下腹部に流れて陰唇を開くようにして流れ去っていった。
椿はまたも達しそうになったが、懸命に堪えた。
その時、「お館様」と椿の間にどのような会話がなされたのかは、記録に残っていない。
その場にいた忍びたちには、特に意味のない言葉が短時間交わされたとしか感じられなかった。
このため記憶に残らず、「お目見え」が終わると同時に忘れてしまったのである。
では、当事者であった「お館様」と椿にとってはどうであったか。
二人もまた、自分たちが何を話したかは覚えていなかった。
二人は、言葉の音圧と気配とを使い、激しく交わっていたのである。
椿は自分が激しく欲情していると同時に、畳に座ったその時から「お館様」が勃起していることを感じ取っていた。
椿の体は「お館様」の前で平伏していたが、その精神は裸に剥かれ、両手両足を拡げられ「お館様」に視姦されていた。
「お館様」は言葉で椿の陰唇を開き、その体の奥の奥まで覗き込もうとする。
椿は見られることに快楽を覚えつつ、見られまいと体をよじる。
だがついには「お館様」の力に抗しきれず、そのすべてを晒してしまうことになった。
「ああ…そんな…恥ずかしい…」
椿は生まれて初めて、心の底から羞恥した。
男忍びに「処女」を散らされた時も、椿は確かに羞恥していたのだが、男の欲情を昂ぶらせるための演技もいくらかは含まれていた。
だが今は演技もなにもない。
文字通り生まれたばかりの素裸である。
生まれたままの姿と羞恥だけがそこにある。
「お館様」はそんな椿の体の感触を隅々まで確かめ、舐り続けた。
椿の頭の芯が痺れる。
やがて「お館様」は椿の両脚を大きく開き、そこに怒張しきった己の男根を押し付けてきた。
先端部からはふつふつと粘性の高い液体が溢れてきてるのが、椿には見えた。
「お、お館様、そ、そんな…椿は、恥ずかしゅうございます…ああっ!」
椿は抵抗したが、「お館様」は椿の体を押し分けてその中に入ってきた。
熱くて硬いものが体内にみしみしと押し入り、椿は背筋を反らしてびくびくと震える。
現実の椿は白砂に平伏したままであり、「お館様」は階上で静かに座っているだけである。
周囲の忍びたちにはそうとしか見えなかった。
だが二人は自分たちが虚空で激しく絡み合い、腰を動かし合う姿を感じていたのである。
妄想かも知れない。幻想かも知れない。
だが二人が寸分違わず同じ夢を見ているのならば、それはもう現実と何の違いもない。
「お館様」との精神の交わりで、椿は五度達した。
「お館様」も五度己を椿の中で解き放った。
周囲の忍びたちからすれば、数呼吸分の時間しか流れていなかったが、二人にとっては一夜に等しいものに感じられていた。
やがて「お館様」は立ち上がり、しずしずと館の奥へと戻っていった。
椿は下を向いたまま立ち、教師役のくのいちにいざなわれて白砂を後にした。
椿の股間はまだ濡れており、痺れたような感覚が残っていた。
椿はまた、「お館様」が下帯の中に膨大な量の精を放っていたことを知っていた。
「『お館様』は何のためにあんなことをなさったんだろう……?」
椿の胸に、ふとした疑問が湧いた。
椿は必死に考えをめぐらしたが、どんなに考えてもわからない。
わからないが、ただひとつだけ確かなことがある。
それは……
「『お館様』。椿は……貴方様をお慕い申し上げております」
くのいち椿は、恋に落ちた。

二.琴野井
くのいち椿は、淫賀の里を離れ、くのいちとしての務めを果たすようになった。
その仕事は、誘惑と暗殺である。
いや、この二つを並べて語るのは間違っているだろう。
あくまでも暗殺が目的であり、誘惑はその手段に過ぎない。
だがか弱い女の身では、目標に近づくことができない。
近づけたとしても相討ちでも覚悟しなければ敵の息の根を止めることはできないだろう。
確実に仕留めるには、敵を寸鉄帯びてない状態にしなければならない。
そのためには自らも肌を晒し、合わせねばならなかった。
裸と裸で相対しても、こちらは女であちらは男。
まだ対等の勝負は挑めない。
己の肉体に溺れさせ、夢うつつの境地に誘わなければ、相手を討つことはかなわなかった。
ただし一度その状況に持ち込まれたら、大部分の男は抵抗できない。
普通のくのいちが仕掛けたとしても、そうなる。
ましてや淫賀の里始まって以来の房中術の名手・椿である。
「大部分の男」がいとも簡単に「ほぼすべての男」になった。
椿は手裏剣を得物に使う。
手裏剣と言っても十字形のそれではない。小ぶりの棒手裏剣だ。
それを普段は膣内に隠しておく。
鼻の下を伸ばした敵の目前で着物を脱ぐ際に、こっそりと手裏剣を抜き、布団の下に隠しておくのだ。
それから椿は手管を尽くして、男を誘惑する。
口、舌、腋、胸、乳首、臍、陰門、さらには尻の間までのあらゆる体の部位を使い、陰茎を刺激する。
敵は陰茎を摩擦されつつ、椿の体が発する香りにも酔う。
椿は普段から人の体を麻痺させる一種の毒薬を服用し、汗とともに放つことにより、相手を酩酊状態に追い込むのだ。
毒は椿の体との相性がよく、汗と混じると得も言われぬ芳香を放つのだ。
毒は汗だけではなく愛液にも混じる。
椿に挿入した相手は、とろとろと溢れ出る蜜に混じる毒により、次第に体の自由を奪われていく。
毒に詳しい忍びが相手だった場合でも、椿のこの術に抵抗することはできない。
というのは椿の性器は生まれた時に産婆が驚いたほどの名器であり、一度咥えこまれた男の魔羅は、極楽浄土もかくやと思われる快楽に囚われ、他のことを一切考えられなくなってしまうからだ。
相手の目が虚ろになった頃合いを見計らい、椿は隠しておいた棒手裏剣を握る。
同時に性器で相手の魔羅を強く締める。
これで男は射精する。
つまり最も無防備な状態となるのだ。
椿は魔羅を性器で締め上げながら、棒手裏剣で相手の喉を突く。
以上は淫賀の里に伝わる「触手裏剣」と呼ばれる術である。
本来は敵と交合し、敵が達した瞬間に棒手裏剣で突く、という術であった。
自分が望む時に自在に相手に射精させ、自らは達せずに理性を保つ、という前提があるため、普通のくのいちにできる技ではない。
椿はこの困難な技に、毒という要素を取り込み、さらに確実に敵を仕留められるようにした。
自らの特殊な体質を前提としているため、他のくのいちにできる技ではない。
この唯一無二に磨き上げられた技を使い、椿は幾多の目標を冥土に送り込んだ。
とは言うものの、人はただ機械的に人の命を絶ち続けることはできない。
椿も人の子、しかも年端も行かぬ娘である。
最初は里の命令であるからと行っていた暗殺ではあるが、繰り返すうちにかすかにではあるが嫌気が差すようになる。
「琴野井、ですか……?」
主命を受けて暗殺の務めを果たすようになってから二年ほど経ったある日、椿は里で新しい任務についての説明を受ける際、聞いたことのない言葉を聞いた。
「知らぬのか?」
「はい」
椿に「琴野井」という言葉を投げかけたのは里でくのいちの束ねを行っている老女だった。
女ながらに中忍に相当する扱いを受けており、下忍相当の椿からすれば常に平伏して相対しなければならない存在だった。
「ほっほっほ。面白い話よのう。『琴野井』に最も近いくのいちが、『琴野井』のなんたるかを知らぬとは」
束ねの老女は、笑いながら話してくれた。
「琴野井」は、淫賀の里のくのいちの最上位の称号である。
体術・毒の扱い・房中の術のいずれにおいても、同じ時期のどのくのいちよりも隔絶した技量を持つものに与えられたという。
「じゃがここ五十年ほど、誰も『琴野井』を名乗らせてもらえなんだわ」
つまるところ位が要求する水準の技を持ったくのいちが生まれなかった、ということである。
しかし、ここに椿がいる。
椿の技・資質は五十年どころか百年に一人のものであり、しかもまだまだ伸びしろがある。
あと少し実績さえ積み上げれば、「琴野井」の位を授けられても不思議ではない、いや授けられない方が不思議だ、と束ねは語った。
「『琴野井』になれば位はわしよりも上じゃ。座敷に上がってお側近くで『お館様』にお目見えすることもできようぞえ」
椿が多少やつれて見えたので、老女としては彼女をいたわり奮起させる目的でこう話したのであろう。
束ねは椿を有能なくのいちとして認めており、里の優秀な道具として愛情を感じてはいた。
老女が期待したほど、椿は喜んだようには見えなかった。
だが実際は、「お館様」の名を聞いただけで体を濡らしてしまっていたのである。
自分がその側近くに寄ることができるという希望は、彼女を絶頂に導くのに十分であった。
くのいちに限らず、忍びは自らの感情・行動を人に悟られないように務める。
達人になればそうした防衛機能は、意識せずとも自動的に働く。
椿もこの時無意識にこれを発動していたため、老女にはさほど喜んだようには見えなかったのだ。
「お館様にまた会える……」
老女のもとを辞し、年に数日寝泊まりするかどうかの自分の家に帰ると、椿はほうっとため息をついた。体はまだ濡れている。
念の為に椿はくのいちの束ね以外の忍びからも、「琴野井」についての情報を集めておいた。
子供の頃から自分を手塩にかけて育ててくれた束ねを信頼していないわけではないが、何事についても裏を取ってしまうのが忍びの性というものだ。
束ねの話していたことは、おおむね事実だった。
一つだけ事実ではなかったのは、「お目見えすることもできようぞえ」という一言である。
「琴野井」は、「お館様」を除く里の忍びの最上位である三人の上忍よりも格上とされていた。
「お目見えできようぞえ」ではなく、確実にお目見えが可能なのだ。
そうでなければ上忍ですら「お館様」の側近くに寄ることはできなくなる。
「上忍様方よりも高位であれば……ひょっとして……「お館様」のご寝所に侍ることも許されるかも……」
椿の手は、彼女自身も知らないうちに、着物の裾を割っていた。
一般庶民の女たちとは違い、くのいちは着物の下に男同様の下帯を締めている。
一定の長さの木綿布は忍びの活動のありとあらゆる局面で役に立つ。
それだけではなく、膣内と直腸内を、非常の際に使う隠し道具の物入れとして使えるようになる。
下帯がないと、少しの衝撃で中に収めたものが飛び出してしまう。
特に膣内の場合、発情して濡れてしまうと滑り落ちる。
実際、この時も椿の膣内から、「仕事道具」である棒手裏剣がこぼれ落ち、ごとりと床で音を立てた。
「お、お館様と……ま、また……」
椿の手は下帯を瞬時に外していた。
湿り気を帯びた白い木綿がはらりと椿の足元に落ちた。
下帯に覆われていた部分から柔らかな湯気が上がり、芳香が室内に拡がる。
椿は夢中になって、右手で股間に差し入れ、秘裂に隠された快楽の芽を、指先で転がした。
左手は胸元に差し入れ、まだ成長途中の乳房を揉みしだく。
股間から、淫靡な水音が聞こえ始めた。
「お、おやかた……さま……」
椿は自身が「お館様」に犯されている姿を想像しながら、自慰を続けた。
性についての知識が尋常ならざるくのいちの妄想であるから、椿の脳裏の「お館様」は、常人の妄想に登場する理想の性交相手からは想像もできないほどに現実のそれに近い。
後世の言葉を用いるのならば、それはオナニーではなくエアセックスだ。
椿は、自分の指を一気に三本、膣内にねじ込んだ。
もちろん椿の脳裏においては、それは自分の指ではなく「お館様」の陽根である。
「ああっ……あっ……お館様……もっと奥を……もっと激しく……」
椿は懐から乳房をまろび出させ、柔らかな肉塊を突き破って飛び立っていきそうな程屹立した乳首を自分の舌で舐め始めた。
「ん……んふっ……んんっ……んちゅっ……」
乳首を吸い、指で膣を激しく責め立てる。
椿の直腸にはまだ「忍び道具」が入っている。
こちらは棒手裏剣ではなく、毒薬を収めた竹筒であった。
毒は暗殺の相手に用いるだけではなく、いざという時の自害用でもある。
指先……いや椿の脳裏においては「お館様」の陰茎だが……が膣と直腸のさほど厚くはない肉壁を通し、竹筒とごりごり擦れ合う。
「お、お館様……もっとっ……」
くのいちの「仕事」の際は快楽に溺れつつも(そうでなければ相手を酔わせることはできない)、どこか理性を残しておかなければならないのだが、自らを慰める場合はそんな心得など放り投げてかまわない。
椿はただひたすらに肉体の快楽を追い求め、手指を動かした。
「ああっ……ああ……お館様……椿は……椿は……」
絶頂の時が迫る。
椿の手指はさらに激しく、おのれの女を感じられる部分を刺激する。
子宮の奥に、熱い塊が生まれる。
それは椿の情欲を吸い取りながら急速に膨張する。
椿は思う。
このままでは壊れてしまう。
「……でも……いいっ……壊してください……お館様っ!」
頭の中が真っ白になり、椿の中で膨らんだ熱い塊が爆発する。
椿は、達した。
椿の膣口から噴水のように愛液がほとばしったのだが、椿はそれに気づかなかった。
「ああっ……あっ……ああ……」
椿はしばらく絶頂の余韻に浸っていたが、やがてそれも潮を引くように静かに消え去っていく。
「お館様……」
虚ろになった目で、自分の指先を見つめ、椿はつぶやいた。
「お慕い申し上げております…」
三.花と修羅
さらに二年の月日が流れた。
くのいち・椿は数え切れないほどの武将を暗殺した。
「触手裏剣」の技を使い、最後に棒手裏剣で喉を突く、という殺しの手順はこれまで通りだが、技そのものがさらに精緻に磨き上げられていった。
すべての相手が椿の名器に酔いしれ、生まれてこのかた感じたことのない最上の悦楽を感じつつ、椿に喉を貫かれることになる。相手は自分が殺されたことにすら気づかない。
椿は棒手裏剣に細工をし、その先端に細く鋭い針を仕込むようにしていた。
針の先端を出したままでは普段膣内に隠しておけないので、普段は手裏剣の本体に収まるようにしておき、強く握りしめると突き出すようにしたのだ。
この細工により、喉の傷跡が目立たなくなった。
「仕事」の翌朝、敵大名の家臣は、悦楽に蕩けきった表情を浮かべた主君の遺骸を、寝所で発見することになる。
殺された当初はおびただしい精汁を放っていたのだが、椿は立ち去る際にそのすべてを片付けていっている。
寝間着もきちんと着せているので、腕のいい医者が検死をしない限り、「自然死」ということにされてしまうのだ。
ごくまれに、寝所の中に漂うかすかな栗の花の匂いに気づく腰元などがいる。
それは間違いなく敵方のくのいちが化けた姿なので、天井裏に潜んでことの結末を見届けていた椿の手により、数日のうちに始末されることになる。
つまり椿の仕事は、それが暗殺だとは気づかれないようにまで磨き上げられていた。
暗殺だとわからなければ椿の存在も歴史の闇の中に消え、誰もそれに気づかなくなるはずである。
だが蛇の道は蛇。
表の世界で「仕事」が見えなくなればなるほど、裏の世界では椿の名とその恐るべき手腕は広く知られるようになっていった。
裏の世界とはいえ、そこらの下忍風情に知られたわけではない。
ほんの一握りではあるが、各地に散らばる忍びの里の棟梁たちに知られたのである。
つまるところ椿の忍びとしての評価は、「本物」になっていったと考えて良い。
そうした評価の上昇に伴い、淫賀の里の忍びの椿に対する態度も変化していった。
まず、上忍の椿に対する扱いが丁寧になった。
今では里の中で椿に出会うと、軽く会釈をする上忍すら出てくる始末である。
それはもちろん、椿が程なく、自分たちよりも上位である「琴野井」に任じられるであろう、と見越しての態度であった。
微妙な媚を含んではいるのだが、それに対し嫌らしさを感じる方向に、椿の人格は歪んではいなかった。
会釈をしようとする上忍に驚き慌て、その場に平伏して失礼しました失礼しましたと額を擦り付けたのである。
これには上忍も苦笑いをし、椿への好意を抱きつつその場を去るしかなかった。
つまるところくのいちでない時の椿は、ごく普通の心根の優しい器量良しの小娘にすぎなかったのだ。
だが本性が素直で優しいほど、忍びという異常な仕事は当人の人格を傷つける。
全体に渡って浅く傷をつけるのではなく、普段は理性によって隠されている人格のちょっとした影の部分を、深く抉るのであるから始末が悪い。
殺された当人が法悦の極地に達したまま意識を消したとしても、「人を殺めた」という罪悪感は、椿の心に積み重なっていく。
「仕事のためだ」と割り切れるほど、椿の本性は荒んではいない。
そうであるにも関わらず、椿が仕事を続けたのは、ひとえに「認められれば琴野井になれる」と信じていたからだ。
最高のくのいちとしての名誉が欲しかったわけではない。
その名を得れば「お館様」の側に寄れる、とただひたすらそれだけを思い描き、任務を果たし続けたのだ。
椿は仕事をする度に、特定の男に抱かれるわけだが、それについては良心の呵責を感じたことはない。
仕事でするあれと「お館様」との媾合とは、似て非なるものなのだ。
やがて殺すことになる敵大名との行為では、椿は心の奥底の大事なところを与えたことは一度もない。
だが肉のふれあいこそなかったものの、あの時の「お館様」との交わりにおいては、椿は自分のすべてを晒しきった。
「お館様」もそれを認めてくださったに違いない、こう信じている。
里においても任務で男に抱かれることにつきどうこう言うものは一人もいない。
強いて言うなら、そのことを一番気にしているのは椿であり、その椿にしてもこの程度なのだ。
椿の精神を削ったのは、ただ純粋に「人を殺す」ということの罪悪感だった。
あと何人殺せば、琴野井になれるのか。五人か、十人か。
「いつまで待てばよろしいのでしょうか……お館様。椿は人を殺すより、お館様のややを産みとうございます……」
何気なく口にしたこの一言が、椿の狂気を加速することになった。
耐えきれない辛い現実から逃れるために夢を見る。
これは人ならば誰でもがすることである。
だが夢は見たらすぐに忘れられ、消え去るものである。
だから多くの人は夢には執着せず、現実に向き直って生きようとする。
しかし、夢が形を持ってしまい、容易には消えなくなったらどうか。
人はその夢に執着するだろう。
そしていつまで経っても叶わない夢と、あいも変わらず自分を責めさいなむ現実との間に、苦痛を深めていく。
愛しい男に抱かれたい、できることならその子を産みたい。
女であれば当然の夢を見ることが、くのいち・椿には許されない。
椿は悩んだ。
悩みはすぐに体に出た。
ほんの三日程で椿の頬はげっそりとこけ、目の下には隈ができた。
虚ろな表情でぎょろぎょろと目だけ動かすようになってしまった。
「繋ぎ」のために椿のもとを訪れた下忍は仰天した。
彼もまた根は善良な男であったため、椿に次の仕事を取りやめ一度里に戻るようにと勧めた。
「でもお仕事なので……」
椿はそう言って、任務に向かおうとしたが、下忍は全力で引き止めた。
「そうは言うがお前さん鏡を見たかい? その面ではとてもではないが大名に惚れさせることはできない。悪いことは言わない。里に戻るんだ。中忍の方々が何か言ってもわしがすべて被ってやるから。ささ」
下忍に背中を押されるようにして、椿は里に戻った。
意外なことに、里の誰もが椿を咎めなかった。
大方は椿の心根を知ったために彼女に好意を抱いており、そうでないごく一部も今の椿の顔を見て、「これなら任務は果たせまい」と感じたからだ。
中忍は同情半分、任務への不適格性半分と判断し、上忍たちは私情を交えず純粋に不適格事項が発生した故の自主的な任務中断と判断した。
上忍たちの興味は、すぐに得難い道具であるくのいち・椿をどうやってまた使えるようにするか、ということに移った。
情は全く含まれなかったが、結果的に情に流されたのと同じ結果となる。
三人の上忍のうち、一番年かさの忍びが、「お館様」の元へ向かった。
なぜか「お館様」は居館におらず、上忍は探し出すのに苦労した。
複数の中忍に命じ、その配下の下忍を動員して網を張らなければ見つけられなかったというのだから、尋常な話ではない。
多少の違和感を感じつつ上忍は、これまた珍しくうつむいて下を見つめる「お館様」をかき口説き、「お願いですから椿に会ってやってくだされ」と頼み込んだ。
「お館様」は終始黙っていたが、最後に小さく「諾」とだけつぶやいた。
「公式の対面とはせぬ。わしが庭に出た時に偶然出会ったという態にせよ」
さらに「お館様」は誰も立ち会わせずにひとりで椿に会う、と言い張った。
上忍は「それはとんでもない」とまた汗をかきつつ「お館様」を説き伏せ、ようやく上忍たちとくのいちの束ねを含む五人ほどを立ち会わせることを認めさせた。
腑に落ちないことが多すぎた。
上忍は首を捻りながら立ち会うことを許されたものどもを呼び集め、「お館様」の言葉を伝え対面の日取りを決めた。
あまり先にすると椿の「壊れ」が進んでしまい里の損に繋がるので、可能な限り早くしようということになった。
対面の日が来た。
「お館様」が来る予定よりもだいぶ前から、椿は庭園の指定された場所に平伏をしていた。
「偶然会った態」ではあるがそれはあくまでも口実である。
他の貴族同様、腿痴家の当主に対しては、然るべき礼儀というものが必要である。
そういう時代であった。
「お館様」の気配が近づく。
だが以前のように、椿にずかずかと近づき、椿の精神体を押し倒す、という感じではない。
何かを必死に堪えているような、押し殺した気配であった。
庭園は竹で結わえた柵に囲われている。
その片隅にあるやはり竹製の小さな門が開いた。
予定では「お館様」がゆっくりと椿に近づき、一言二言言葉をかけるはずだった……しかし。
「!」
門が開いた、と感じた瞬間、椿は唇が熱く湿ったもので覆われるのを覚えた。
さらに熱くぬめったものが唇を割り、椿の舌と歯をねめまわす。
「お、お館様!」
周囲の上忍どもが驚きの声をあげたその瞬間には、「お館様」は椿を全裸にし、庭園に組み敷いていた。
当人も全裸となっている。
ちなみに、椿は「お館様」に対して非礼であるからと、いつも膣内と直腸内に入れている棒手裏剣と毒竹筒は外していた。
「すまなんだな。椿」
椿の唇から自分の唇を離すと、「お館様」はそう言った。
だがすぐにまた椿の唇をむさぼる。
「すべてわしが悪かった。そちと初めてあったあの時、わしはそちに懸想してしまったのじゃ」
「お館様」が自分の体を本心から求めていたことは、あの時はっきりとわかった。
だがどうして体を求めたのかがわからなかった。
その理由が今、わかった。
「わしはそちが欲しかった。妻として側に置きたかった。じゃがそちは百年にひとり出るかどうかというくのいちじゃ。わしごときの妻にしてしまえば、里は忍び仕事ができぬ」
「お館様」はそう言いながら激しく椿の乳房をまさぐった。
椿の乳首は、とうに張り裂けそうなほど勃起している。
「わしは悩み、里のためにそちとはできるだけ会うまいと考えた。わしなぞに会わず、ひたすら仕事に打ち込めば、そちのためにもなると思ったのじゃ。じゃが、すべて間違いじゃった。すべて間違いだったのじゃ」
椿の中にむくむくとある感情が沸き起こる。
それは愛そのものであった。
心から一点の曇りもなく、「お館様」を愛おしいと思った。
椿は「お館様」を抱きしめた。
「わしは椿に懸想していることを隠さぬ。誰にも隠さぬ。者共見ておれ、わしは今から椿と媾わうぞ!」
「お館様」は凛と声を張り上げると、怒張した魔羅を椿の膣内に突き入れた。
椿と「お館様」は、それから三日三晩に渡り交わり続けたという。
周囲にいた上忍たちからすれば、ある意味迷惑な話であった。
彼らは立場上、その場を離れることができない。
老人とはいえ、かつては現役の忍びとして活躍していた面々である。
三日三晩立ち続けるぐらいのことは、今でも平気でできる。
だがそれだけではなくあたりを憚ることなしに交わり続ける男女の監視となると、話は変わってくる。
椿と「お館様」の媾合の激しさに当てられ、「束ね」の老女は年甲斐もなく頬を染めのぼせて倒れてしまった。
他の上忍たちも、袴の前に山を作っていたという。
二人はというと、三日目に結合し合ったまま失神していた。
腰から下は精液と愛液の混じった池に浸っていた。
上忍たちは二人の体を池の水で清め、白い湯帷子を着せ、一つの布団に寝かせてやった。
やがて椿が目覚める。
「お館様」は先に起きていて、椿の寝顔を眺めていたようだ。椿は恥じらい、頬を染めた。
起きた後、二人はじっと見つめ合っていたが、やがて同時に声をかけあった。
「里を抜けよ」
「里を抜けたいと思います」

言葉の中身はまったく同じだった。
二人はこう言った時に、お互いの心中を理解したが、読者には多少の説明を加えねばなるまい。
「お館様」が椿に語って聞かせた理由というのは、こんなものである。
椿の技は前人未到の境地に達しつつある。
これをさらに育てていくことが、椿にとって何よりの幸せというものであろう。
自分はひとりの忍びとして、椿を見守っていきたい。
椿が里にいると、妻にしたくて堪らなくなってしまう。
だから里を出よ、と。
椿の思いも同じであったが、「お館様」を優れた術者であり里の指導者と認め、自分の存在が「お館様」を惑わすことになるだろう、という分析が付け加えられていた。
さらに椿の体には、暗殺に使った毒が蓄積している、という問題がある。
先日のように「お館様」と交わり続けたら、「お館様」の寿命を縮めてしまう。
二人は互いに見交わし、ゆっくりと頷いた。
「お館様」が枕元にあった短刀を抜き、椿に斬りつける。
短刀は椿の胸元の皮一枚を切り裂き、鮮血を散らした。
「誰かある! 謀反じゃ! くのいち椿の謀反である! 椿を捕らえよ!」
「お館様」が叫ぶ。
互いが納得しているとはいえ、「抜け」を平和的に許すなどということは、忍びの里においてできることではなかった。
故に狂言で「お館様」に背いたということにする必要があったのだ。
上忍たちが配下を連れて集まる前に、椿は里から姿を消していた。
林の中を風よりも速く走る椿は、ふと自分の懐に一通の書状が押し込まれいたことに気づく。
走りながら開いて見ると、それは「お館様」の手によって書かれた認可状であった。
「くのいち椿、これより『琴野井』を名乗ることを許し参らせ候」
椿は走りながら泣いた。
その後数十年。
抜け忍となったくのいち「琴野井」の伝説が、忍びの里の一部に密かに伝えられた。
「琴野井」はいつまでも若く美しく、狙った獲物は確実に仕留めていたという。
だがその姿を実際に見た、絶品と言われた性器を味わったと語る生者は、どこにもいなかった。
この商品に対するお客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
その他のオススメ商品
オナホ屋さんの本気汁!! ヌメリの皇太子!!ぬめッパ!...
販売価格(税込): 831~2,200 円
【オナホ文学】 ダブルフェラ魔チオ 「魔女のおはな...
販売価格(税込): 0 円
【オナホ文学】 被虐のアリューネ~忘我~ 「輪廻の...
販売価格(税込): 0 円
【オナホ文学】 わからせ鬼退治2
販売価格(税込): 0 円
【オナホ文学】 被虐のアリューネ~悲恋~ 「悲劇の...
販売価格(税込): 0 円
【オナホ文学】 佐藤のアナル is revived
販売価格(税込): 0 円